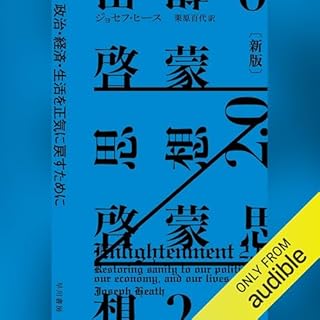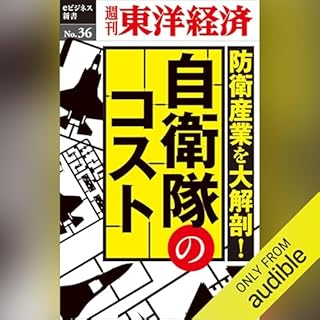現実はいつも対話から生まれる
カートのアイテムが多すぎます
カートに追加できませんでした。
ウィッシュリストに追加できませんでした。
ほしい物リストの削除に失敗しました。
ポッドキャストのフォローに失敗しました
ポッドキャストのフォロー解除に失敗しました
Audibleプレミアムプラン30日間無料体験
¥2,700 で購入
-
ナレーター:
-
入江 直樹
概要
内容
対話型組織開発、教育、心理療法etc.
注目を集める「社会構成主義」最良の入門書
ここに対立を超える鍵がある。
社会構成主義の基礎的な考えはとてもシンプルなようでいて、非常に奥深くもあります。
私たちが「現実だ」と思っていることはすべて「社会的に構成されたもの」です。
もっとドラマチックに表現するとしたら、そこにいる人たち が、「そうだ」と「合意」して初めて、それは「リアルになる」のです。
あなたは懐疑的にこう反応するかもしれません。
「死が存在しないという意味ですか? この身体も太陽もこの椅子も?」
私たちはここで、ひとつはっきりさせておかなければいけません。
社会構成主義者は「何も存在しない」とか「現実などない」と言っているわけではないのです。
重要なポイントは、人が「何が現実か」を定めるとき、
常にそれは、あるひとつの文化の伝統から話しているのだということです。
確かに何かは起こりました。けれど、それを描写するには、ある特定の文化の観点を通さざるをえないのです。
つまり、その文化特有の言語だとか、見方、話し方を通して語らざるをえないということです。
たとえば、「彼のお父さんが亡くなりました」ということを描写しようとすると、
普通は生物学的観点から語ることになります。
ここで私たちは「起こったこと」を「特定の身体機能の停止」として「構成」しているのです
(けれども、医療専門家たちの間でもそれを死と確定することには同意が成立しないかもしれません。
移植外科医は、かかりつけの内科医とは別の意見を持っている可能性があります)。
他の文化的伝統においては、「彼は昇天しました」とか「彼は彼女の心の中に住み続けます」とか、
「これは彼の生まれ変わりの新しいサイクルの始まりなのです」とか、
「彼は苦しみから解き放たれました」とか、「彼は、彼が残した功績という遺産の中に生き続けます」とか、
「彼の3人の息子たちに彼の人生は引き継がれます」とか、
「この物体の原子構成が変化したのです」などと語られるかもしれません。
こういったあらゆる文化的伝統の外に出てしまったとしたら、私たちはどのように語ることができるでしょうか?
構成主義者にとっては、「何も存在しない」のではなく、「私たちにとっては何も意味しない」ということなのです。
他の言い方をすると、「私たちの関係性」によって、
私たちの世界は、私たちが「木」「太陽」「身体」「椅子」などと捉えているもので満たされるのです。
もっと広い意味で言えば、お互いにコミュニケーションを取るたびに、
私たちは、この生きている世界を構成していると言えるかもしれません。
私たちが日頃慣れ親しんでいる伝統の中にいつづけるかぎり、人生はそのままでしょう。
たとえば、「男と女」、「貧富」、「教養がある/教養がない」などのように慣れ親しんだ「区別」をしている限り、
人生は、比較的予測できるものであり続けるのです。
しかし私たちは、「当たり前だ」と考えられているものすべてに挑戦することもできるのです。
たとえば、「問題」はすべての人の目に見えるわけではありません。
私たちが「良し」とする世界を構成していて、
私たちが価値を置いていることを実現するのを妨げるものを「問題」と見なしているわけです。
私たちが「問題」として「構成」しているすべてのものを、
「チャンス(機会)」として「再・構成」することはできないでしょうか?
(第1章より)
こちらもおすすめ
-
ダイアローグ 価値を生み出す組織に変わる対話の技術
- 著者: 熊平 美香
- ナレーター: 漆間 朝子
- 再生時間: 5 時間 29 分
- 完全版
-
総合評価8
-
ナレーション7
-
ストーリー7
<推薦コメント>◎――Zホールディングス株式会社 Zアカデミア学長 伊藤羊一氏 仕事する上で、常に横に置いておきたい一冊。
-
-
未来をつくるための対話のマナー本📕
- 投稿者: 田邊輝真 日付: 2023/08/29
著者: 熊平 美香
-
人を動かすナラティブ なぜ、あの「語り」に惑わされるのか
- 著者: 大治 朋子
- ナレーター: 谷合 律子
- 再生時間: 11 時間 41 分
- 完全版
-
総合評価18
-
ナレーション18
-
ストーリー18
各メディアで紹介され、話題沸騰! 【新聞】 毎日新聞「今週の本棚」(2023年8月19日)評者:永江朗氏 読売新聞「本よみうり堂」(2023年9月3日)評者:堀川惠子氏
-
-
ナラティブへの盲信が招くリスク
- 投稿者: CHR 日付: 2024/09/27
著者: 大治 朋子
-
リフレクション(REFLECTION) 自分とチームの成長を加速させる内省の技術
- 著者: 熊平 美香
- ナレーター: 岡村 美里
- 再生時間: 6 時間 59 分
- 完全版
-
総合評価31
-
ナレーション25
-
ストーリー25
すべての経験が糧になる、リーダーの新・必須スキル!【意見】【経験】【感情】【価値観】で自分を知り、未来に活かす!
-
-
ナレーションの聞きやすさ
- 投稿者: xxx 日付: 2025/02/11
著者: 熊平 美香
-
「対話と決断」で成果を生む 話し合いの作法
- 著者: 中原 淳
- ナレーター: 遠藤 純平
- 再生時間: 5 時間 35 分
- 完全版
-
総合評価30
-
ナレーション26
-
ストーリー26
●リーダーしか発言しないチーム、結局何も決まらない会議……●形だけの対話から脱却し、成果を生む「話し合いの作法」とは?●言いたいことが言い合える職場・組織をつくる全技法!
-
-
話し合いをしたら行動も決める
- 投稿者: TKHR 日付: 2023/11/12
著者: 中原 淳
-
世界は贈与でできている 資本主義の「すきま」を埋める倫理学
- 著者: 近内 悠太
- ナレーター: 平川 正三
- 再生時間: 5 時間 45 分
- 完全版
-
総合評価57
-
ナレーション54
-
ストーリー54
これが、ニュー・ノーマル時代を切り拓く哲学書。
-
-
一部どうでもいいような事があると思った
- 投稿者: おおおおおお 日付: 2026/02/13
著者: 近内 悠太
-
Love
- A Very Short Introduction
- 著者: Ronald De Sousa
- ナレーター: Paul Heitsch
- 再生時間: 4 時間 23 分
- 完全版
-
総合評価0
-
ナレーション0
-
ストーリー0
Although there are many kinds of love, erotic love has been celebrated in art and poetry as life's most rewarding and exalting experience, worth living and dying for and bringing out the best in ourselves. And yet it has excused, and even been thought to justify, the most reprehensible crimes.
著者: Ronald De Sousa
-
ダイアローグ 価値を生み出す組織に変わる対話の技術
- 著者: 熊平 美香
- ナレーター: 漆間 朝子
- 再生時間: 5 時間 29 分
- 完全版
-
総合評価8
-
ナレーション7
-
ストーリー7
<推薦コメント>◎――Zホールディングス株式会社 Zアカデミア学長 伊藤羊一氏 仕事する上で、常に横に置いておきたい一冊。
-
-
未来をつくるための対話のマナー本📕
- 投稿者: 田邊輝真 日付: 2023/08/29
著者: 熊平 美香
-
人を動かすナラティブ なぜ、あの「語り」に惑わされるのか
- 著者: 大治 朋子
- ナレーター: 谷合 律子
- 再生時間: 11 時間 41 分
- 完全版
-
総合評価18
-
ナレーション18
-
ストーリー18
各メディアで紹介され、話題沸騰! 【新聞】 毎日新聞「今週の本棚」(2023年8月19日)評者:永江朗氏 読売新聞「本よみうり堂」(2023年9月3日)評者:堀川惠子氏
-
-
ナラティブへの盲信が招くリスク
- 投稿者: CHR 日付: 2024/09/27
著者: 大治 朋子
-
リフレクション(REFLECTION) 自分とチームの成長を加速させる内省の技術
- 著者: 熊平 美香
- ナレーター: 岡村 美里
- 再生時間: 6 時間 59 分
- 完全版
-
総合評価31
-
ナレーション25
-
ストーリー25
すべての経験が糧になる、リーダーの新・必須スキル!【意見】【経験】【感情】【価値観】で自分を知り、未来に活かす!
-
-
ナレーションの聞きやすさ
- 投稿者: xxx 日付: 2025/02/11
著者: 熊平 美香
-
「対話と決断」で成果を生む 話し合いの作法
- 著者: 中原 淳
- ナレーター: 遠藤 純平
- 再生時間: 5 時間 35 分
- 完全版
-
総合評価30
-
ナレーション26
-
ストーリー26
●リーダーしか発言しないチーム、結局何も決まらない会議……●形だけの対話から脱却し、成果を生む「話し合いの作法」とは?●言いたいことが言い合える職場・組織をつくる全技法!
-
-
話し合いをしたら行動も決める
- 投稿者: TKHR 日付: 2023/11/12
著者: 中原 淳
-
世界は贈与でできている 資本主義の「すきま」を埋める倫理学
- 著者: 近内 悠太
- ナレーター: 平川 正三
- 再生時間: 5 時間 45 分
- 完全版
-
総合評価57
-
ナレーション54
-
ストーリー54
これが、ニュー・ノーマル時代を切り拓く哲学書。
-
-
一部どうでもいいような事があると思った
- 投稿者: おおおおおお 日付: 2026/02/13
著者: 近内 悠太
-
Love
- A Very Short Introduction
- 著者: Ronald De Sousa
- ナレーター: Paul Heitsch
- 再生時間: 4 時間 23 分
- 完全版
-
総合評価0
-
ナレーション0
-
ストーリー0
Although there are many kinds of love, erotic love has been celebrated in art and poetry as life's most rewarding and exalting experience, worth living and dying for and bringing out the best in ourselves. And yet it has excused, and even been thought to justify, the most reprehensible crimes.
著者: Ronald De Sousa
-
ジョン・デューイ: 民主主義と教育の哲学
- 著者: 上野 正道
- ナレーター: 井上 智博
- 再生時間: 7 時間 22 分
- 完全版
-
総合評価8
-
ナレーション8
-
ストーリー8
教育とは何かを問い,人びとがともに生きる民主主義のあり方を探究し実践した,アメリカを代表する思想家デューイ.彼の構想したコモン・マン,
-
-
聞きやすい
- 投稿者: 匿名 日付: 2023/08/29
著者: 上野 正道
-
プリズン・サークル
- 著者: 坂上 香
- ナレーター: 兼安 愛海
- 再生時間: 10 時間 26 分
- 完全版
-
総合評価31
-
ナレーション28
-
ストーリー28
「私たちもまた、泣いているあの子を見捨てた加害者のひとりではなかったか?」(上間陽子さん・教育学者)受刑者が互いの体験に耳を傾け、本音で語りあう。そんな更生プログラムをもつ男子刑務所がある。
-
-
加害者は、何かの被害者。
- 投稿者: torys 日付: 2025/05/25
著者: 坂上 香
-
Chemistry for Breakfast
- The Amazing Science of Everyday Life
- 著者: Dr. Mai Thi Nguyen-Kim
- ナレーター: Raechel Wong
- 再生時間: 5 時間 34 分
- 完全版
-
総合評価0
-
ナレーション0
-
ストーリー0
Chemistry for Breakfast is a perfect book for anyone who wants to deepen their understanding of chemistry without having prior knowledge of the science. With Mai as your guide, you'll find something fascinating everywhere around you.
-
職場で傷つく~リーダーのための「傷つき」から始める組織開発
- 著者: 勅使川原 真衣
- ナレーター: 茶谷 英司朗
- 再生時間: 5 時間 28 分
- 完全版
-
総合評価21
-
ナレーション20
-
ストーリー20
『他者と働く』『企業変革のジレンマ』宇田川元一氏 推薦「職場で傷ついた人は、企業変革の入り口に立っている。」『「能力」の生きづらさをほぐす』で鮮烈なインパクトを残した気鋭のコンサルタントが、なきものとされてきた「職場の傷つき」に着目し、これからの組織開発のあるべき道筋を探る意欲作。
-
-
言語化してくれてスッキリした
- 投稿者: ししくん 日付: 2026/02/19
著者: 勅使川原 真衣
-
ケアの倫理――フェミニズムの政治思想
- 著者: 岡野 八代
- ナレーター: 新田 えみ
- 再生時間: 11 時間 21 分
- 完全版
-
総合評価13
-
ナレーション13
-
ストーリー13
身体性に結び付けられた「女らしさ」ゆえにケアを担わされてきた女性たちは、自身の経験を語る言葉を奪われ、言葉を発したとしても傾聴に値しないお喋りとして扱われてきた。
-
-
ケア労働は誰がケアしているのか
- 投稿者: いなり 日付: 2024/08/05
著者: 岡野 八代
-
問いかけの作法 チームの魅力と才能を引き出す技術
- 著者: 安斎 勇樹
- ナレーター: 佐藤 充宏
- 再生時間: 7 時間 13 分
- 完全版
-
総合評価58
-
ナレーション51
-
ストーリー51
チームの主体性と創造性を発揮したい、すべてのマネージャー必携!ベストセラー『問いのデザイン:創造的対話のファシリテーション』の著者による最新作
-
-
図??
- 投稿者: ゼン 日付: 2022/01/10
著者: 安斎 勇樹
-
ナラティブカンパニー
- 企業を変革する「物語」の力
- 著者: 本田 哲也
- ナレーター: 日下 純
- 再生時間: 7 時間 3 分
- 完全版
-
総合評価19
-
ナレーション18
-
ストーリー18
戦略PRの第一人者が伝授!ナイキ、ソニー、アマゾン、メルカリほか、豊富な事例に学ぶ「企業と生活者が共に紡ぐ物語」のつくり方味の素冷凍食品:冷凍餃子は
著者: 本田 哲也
-
非暴力主義の誕生
- 武器を捨てた宗教改革
- 著者: 踊 共二
- ナレーター: 高城 亨
- 再生時間: 6 時間 53 分
- 完全版
-
総合評価4
-
ナレーション3
-
ストーリー3
一五二五年,宗教改革の渦中,幼児洗礼を拒むキリスト教の一派が誕生した.異端として迫害されながらも聖書の教えを守り,非暴力を貫いた彼らの信仰は,戦争の止まない現代に生きる私たちに何を語りかけるのか.
著者: 踊 共二
-
この気もち伝えたい
- 著者: 伊藤 守
- ナレーター: 末松 享子
- 再生時間: 18 分
- 完全版
-
総合評価11
-
ナレーション9
-
ストーリー9
コミュニケーションで大切なことは、みんなこの絵本の中に入っています。 キャッチボールのイラストとともに、気もちを伝えるコミュニケーションの秘訣をシンプルに語った、累計部数30万部を超
-
-
シンプルだけど
- 投稿者: つんつん 日付: 2024/06/30
著者: 伊藤 守
-
ビジネスと人権
- 人を大切にしない社会を変える
- 著者: 伊藤 和子
- ナレーター: デジタルボイス
- 再生時間: 6 時間 53 分
- 完全版
-
総合評価4
-
ナレーション3
-
ストーリー3
人を人とも思わないやり方で搾取し蹂躙する社会が国内外の企業活動で生じている.企業は国際人権基準を尊重する責任を負い,国家には人権を保護する義務があり,人権侵害には救済が求められる.
著者: 伊藤 和子
-
働く大人のための「学び」の教科書
- 著者: 中原 淳
- ナレーター: 長塚 コト
- 再生時間: 5 時間 26 分
- 完全版
-
総合評価28
-
ナレーション23
-
ストーリー23
本タイトルで参照する付属資料は以下URLよりダウンロードいただくことができます。
http://download.audible.com/product_related_docs/BK_KANK_000011.pdf
PDF提供元:かんき出版
健康寿命80代まで働く時代、ひとつのスキルや技能で“一生食える”時代ではない。
このことは40代・50代のミドル世代も、20代・30代の若手世代も、うっすら感じている。
しかし「働き続けるために、自分は何をすればいいのか、どうすればいいかわからない」という人は多い。
また「それには、学んで変わっていかなければ...
-
-
学び続ける大切さを教えてくれます。
- 投稿者: 匿名 日付: 2019/03/15
著者: 中原 淳
-
ビジョンプロセシング
- ゴールセッティングの呪縛から脱却し「今、ここにある未来」を解き放つ
- 著者: 中土井 僚
- ナレーター: 小桧山 崇
- 再生時間: 18 時間 17 分
- 完全版
-
総合評価12
-
ナレーション9
-
ストーリー9
「答えがないのに、ゴールを示すべき」 というジレンマを、誰もが抱えている
そのビジョンは、「現在の自分たち」を勇気づけ、 主体性と創造性を解放しようとしているか? 日々のプロセスを問い直すものとなっているか?
-
-
印象に残らない
- 投稿者: 坂口涼太郎系男子 日付: 2026/01/25
著者: 中土井 僚
-
経営の力と伴走支援
- 「対話と傾聴」が組織を変える
- 著者: 角野 然生
- ナレーター: 高城 亨
- 再生時間: 5 時間 40 分
- 完全版
-
総合評価3
-
ナレーション2
-
ストーリー2
企業経営者と支援者が「対話と傾聴」を通じ、本質的な経営課題に気づき、潜在力を活かして自立的な企業変革への道筋をつける伴走支援。
-
-
著者の経営だけに伴わない社会問題に対して通じる哲学を感じました!
- 投稿者: Yuji M 日付: 2024/12/30
著者: 角野 然生
-
Consciousness
- A Very Short Introduction
- 著者: Susan Blackmore
- ナレーター: Zehra Jane Naqvi
- 再生時間: 4 時間 35 分
- 完全版
-
総合評価1
-
ナレーション0
-
ストーリー0
Exciting new developments in brain science are continuing the debates on these issues, and the field has now expanded to include biologists, neuroscientists, psychologists, and philosophers. This controversial book clarifies the potentially confusing arguments, and the major theories, while also outlining the amazing pace of discoveries in neuroscience. Covering areas such as the construction of self in the brain, mechanisms of attention, the neural correlates of consciousness, and the physiology of altered states of consciousness, Susan Blackmore highlights our latest findings.
著者: Susan Blackmore
-
Nietzsche
- A Very Short Introduction
- 著者: Michael Tanner
- ナレーター: Christine Williams
- 再生時間: 3 時間 35 分
- 完全版
-
総合評価1
-
ナレーション0
-
ストーリー0
With his well known idiosyncrasies and aphoristic style, Friedrich Nietzsche is always bracing and provocative, and temptingly easy to dip into. Michael Tanner's introduction to the philosopher's life and work examines the numerous ambiguities inherent in his writings and explodes many of the misconceptions that have grown in the hundred years since Nietzsche wrote "do not, above all, confound me with what I am not!"
著者: Michael Tanner
-
アボリジナル・メッセージ
- 著者: 飯島 浩樹
- ナレーター: デジタルボイス
- 再生時間: 3 時間 39 分
- 完全版
-
総合評価5
-
ナレーション4
-
ストーリー4
何も持たずに豊かに暮らすオーストラリア先住民が教えてくれた幸せ法則とは?所有から共有へ。
-
-
オーストラリアでも一般的に知られていないような素晴らしいストーリー
- 投稿者: Amazon カスタマー 日付: 2025/12/22
著者: 飯島 浩樹
-
啓蒙思想2.0〔新版〕
- ―政治・経済・生活を正気に戻すために―
- 著者: ジョセフ・ヒース, 栗原 百代 (翻訳)
- ナレーター: 田丸 裕臣
- 再生時間: 17 時間 40 分
- 完全版
-
総合評価0
-
ナレーション0
-
ストーリー0
『反逆の神話』のヒース、渾身の書〔政治・経済・生活を正気に戻すために〕右翼/左翼ではなく、正気/狂気に分断され、真実より「真実っぽさ」が跳梁する現代。過激な論争を助長し合理的な議論を破壊するSNS。
著者: ジョセフ・ヒース, 、その他
-
コーチング・マネジメント―人と組織のハイパフォーマンスをつくる (コーチ・エィ監修コーチングシリーズ)
- 著者: 伊藤 守
- ナレーター: 松浦 このみ
- 再生時間: 5 時間 28 分
- 完全版
-
総合評価38
-
ナレーション35
-
ストーリー35
日本における唯一の「国際コーチ連盟マスター認定コーチ」が、理論から実践までを体系的に著したコーチングの「基本書」である。
-
-
ゴール先のゴールを決めること
- 投稿者: Amazon カスタマー 日付: 2025/01/13
著者: 伊藤 守
-
ケアと編集
- 著者: 白石 正明
- ナレーター: 吉田 健太郎
- 再生時間: 6 時間 20 分
- 完全版
-
総合評価8
-
ナレーション7
-
ストーリー7
もはやこれまでと諦めてうなだれたとき,足元にまったく違うモノサシが落ちている.与えられた問いの外に出てみれば,あらふしぎ,あなたの弱さは克服すべきものじゃなく,存在の「傾き」として不意に輝きだす──.
-
-
その人らしく
- 投稿者: Amazon カスタマー 日付: 2025/11/12
著者: 白石 正明
-
チームレジリエンス 困難と不確実性に強いチームのつくり方
- 著者: 池田 めぐみ, 安斎 勇樹
- ナレーター: 辻 留奈
- 再生時間: 4 時間 30 分
- 完全版
-
総合評価4
-
ナレーション3
-
ストーリー3
困難を乗り越えるたびにどこまでもチームは強くなる!不確実性と困難がストレスを生み、逃避行動を起こす。耐える、逃げる、責任転嫁する…自分を守るためのこうした独りよがりのレジリエンスがチームや組織に負のスパイラルを招いていく。
著者: 池田 めぐみ, 、その他
-
問いの編集力
- 思考の「はじまり」を探究する
- 著者: 安藤 昭子
- ナレーター: 佐々木 雅夫
- 再生時間: 6 時間 52 分
- 完全版
-
総合評価29
-
ナレーション28
-
ストーリー28
落合陽一氏 佐渡島庸平氏 推薦! AIが「答え」を出す時代に思考の主導権を取り戻すアルゴリズムが誘導する世界を「問う力」で切りひらく編集工学に基づく知的創造のプロセス…
-
-
本質があるはずなのだが、今の私にレベルには難しい。
- 投稿者: 田邊輝真 日付: 2025/01/27
著者: 安藤 昭子
-
こころの対話 25のルール(ディスカヴァー。トゥエンティワン)
- 著者: 伊藤 守
- ナレーター: 佐藤 充宏
- 再生時間: 4 時間 10 分
- 完全版
-
総合評価34
-
ナレーション28
-
ストーリー27
話を聞くだけでいいのです。あなたの何かが変わります。ほんとうのコミュニケーションは相手の話を聞くことから始まります。
-
-
音量上げて欲しい
- 投稿者: たかたか 日付: 2023/06/21
著者: 伊藤 守
-
防衛産業を大解剖! 自衛隊のコスト
- (週刊東洋経済eビジネス新書No.36)
- 著者: 週刊東洋経済編集部
- ナレーター: 岩見 聖次
- 再生時間: 2 時間 45 分
- 完全版
-
総合評価2
-
ナレーション2
-
ストーリー2
本タイトルには付属資料が用意されています。 ご購入後、PC上でAudibleのホームページを開き、「ライブラリー」をご確認ください。 ※Windows10端末をご利用のお客様は、アプリ上で直接ご覧いただけます。
東日本大震災後、自衛隊の存在感が急浮上している。しかし緊縮財政のなか、防衛予算も右肩下がりが続き、防衛産業にも影響を与えている。防衛産業は、自衛隊におカネが落ちなければ、売り上げも立たない。民生品に転用できない特殊な設備や職人技に頼る部分も多い。今後も発注が減少すれば、そうした人・モノを手放さざるをえなくなる 。
本書では、日本企業がつくる防衛装備の紹介や他国の防衛産業の事例、基地のある町のルポ、武器輸出三原則の問題点、防衛問題に詳しい自民党・石破茂氏へのインタビューなどを通じて、防衛産業のありのままの姿と課題を探った。
著者: 週刊東洋経済編集部