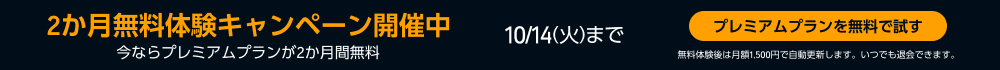#9-1. 「AIは親切な嘘つき?」―生成AIがもたらす3つのリスク
カートのアイテムが多すぎます
ご購入は五十タイトルがカートに入っている場合のみです。
カートに追加できませんでした。
しばらく経ってから再度お試しください。
ウィッシュリストに追加できませんでした。
しばらく経ってから再度お試しください。
ほしい物リストの削除に失敗しました。
しばらく経ってから再度お試しください。
ポッドキャストのフォローに失敗しました
ポッドキャストのフォロー解除に失敗しました
-
ナレーター:
-
著者:
このコンテンツについて
📖内容
今回のエピソードでは、「AIは親切な嘘つき?」生成AIがもたらす3つのリスク をテーマに徹底解説!
AIのメリットと危うさを整理しながら、実際の論文や事例を交えて深掘りします。
まずは生成AIの効果とリスクを整理。知識労働の効率化、創造性の拡張、個別最適化された学習などの利点と並び、ハルシネーション、同調傾向、創作と事実の曖昧化といったリスクを紹介します。
続いて、3つのリスクを詳細に解説。
ハルシネーション:OpenAIの最新論文を参照し、「確率的に自然な文章を生成する」というAIの構造から生じる仕組みを解説。存在しない裁判判例を列挙した弁護士事件などの事例を紹介。 🤏9-1はここまで!
同調傾向:RLHFによる「同意が高評価される」仕組みから、AIが“イエスマン”になりやすい問題を説明。GPT-4oでの過剰同調事例や、エコーチェンバー化の危険性も議論。
創作と事実の曖昧化:AIが事実とフィクションを区別せず生成するため、フェイク記事や偽画像の拡散につながる問題を紹介。検証ツールが効きにくい点や、組織におけるAI利用ガイドラインの重要性も提示。
最後に、AIを使う上で大切なのは「人間の判断を必ず挟む」ことだと強調し、効率化とリスクの両面を踏まえた付き合い方を考察します。
🔖おすすめポイント
AIの利点:効率化・創造性拡張・個別最適化
リスク解説:ハルシネーション、同調傾向、曖昧化の3点セット
OpenAIの最新論文から読み解くハルシネーションの仕組み
実際の事例:裁判での虚偽判例、GPT-4oでの過剰同調、偽記事や偽画像の拡散
利用の指針:「AIに頼り切らず、人間の判断を必ず挟む」ことの重要性
🎙️パーソナリティ
ISHIKAWA @ISHIKAWA696736
浪花祐貴 @naniwan721
まだレビューはありません